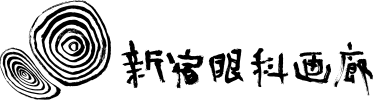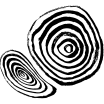〔展示〕
2022年12月2日(金)~7日(水)
12:00~20:00(水曜日~17:00) ※木曜日休廊
「キルトの裾野」
-夏の終わりのキルトパーティー成果展-
増田ぴろよ
入場料:¥500-(入場者特典 / ZINE + ポストカード)
スペースO
〔statement〕
憎しみを昇華し尽くした先に現れた山 : 佐々木ののか
――ペニスを切り刻んで解体し、祈りながら連帯する。
これまでの増田ぴろよの作品群を、かなり乱暴に言い表すことが許されるならば、この一言に尽きるだろう。
増田のアーティストとしてのキャリアのはじまりは2011年、男性器をモチーフにしたテキスタイルを制作することに端を発している。2013年には初の個展『新宿回転ベッド』が眼科画廊で開かれ、2012年頃に制作した男性器をモチーフにしたテキスタイルと、それらを縫い合わせたパッチワーク・クレイジーキルトで飾りつけた電動回転ベッドを展示。2014年には男性器モチーフのテキスタイルを縫い繋げた『キルト』の制作を始める。男性器を表現する素材がテキスタイルである理由は「憎しみを切り刻みたかったから」だ。2015年の『新宿回転ベッド 男犬・MOTHER』では、展示期間を前後期に分け、電動回転ベッドの上で2つの作品を展示した。前期の「男犬」では、男性への信仰と消費との狭間で揺れ動く自分自身を俯瞰しながら見つめ、後期の「MOTHER」では“母”から“娘”へと伝承される呪いをテーマにした展示を開催。会期中は、「犬」と「男」と「母」がベッドの上でぐるぐる回る中、演劇やアーティストトークが行われた。同展示で発表された男性アイドルとの接触目的で大量購入されたCDを、ペニスを模した彫刻に切り刻み貼り付けた「鎮魂ミラーボール」は、偏愛の終着駅とも言える作品だ。
2017年には歌舞伎町の高級クラブで個展『正しい娘。』を開催。水商売という虚構の場に「私って可哀想」という文字を綴ったキルト作品群を展示し、クラブのVIP席にはかつての”推し”被りと共同制作した大作「共闘のブラックホール」が鎮座。それらを「鎮魂ミラーボール」が照らしだす地獄は、あまりにも素直で正しい。同時期に自身のテキスタイルプロダクト「去勢」を立ち上げる。男性器モチーフのテキスタイルを商品化した理由は「怒りを手放したかったから」だとのちに増田は語っている。男性器モチーフの傍らには、常に憎しみや怒りの昇華がある。また、2020年からはキルトの共同制作に着目し、ワークショップを取り入れた個展「キルトパーティ」を定期開催し始めた。
男性への憎しみが渦巻く環境に身を置き、湧き上がる情念を原動力に布を切り刻み、祈るように縫い合わせ、キルト作品をつくる。具体的な人物や出来事を表象しないまでも、キルトは常に、増田の人生ひいては生活に即したものだった。それは今回の展示においても例外ではない。
本展示作品のモチーフは「山」だ。
増田にとっての「山」とは、資本主義とロマンティック・ラブ・イデオロギーの歪み渦巻く「歌舞伎町」からの逃避先なのだという。資本主義も、盲目な恋愛も、焼ききれんばかりに速度を増していく点においては重なり合い、愛情表現として金銭を手渡す折には等価となる。彼女にとって両者は、常に並列する存在なのだろう。
しかし、資本主義とロマンティック・ラブ・イデオロギーこそ、これまでの増田の“主戦場”だったはずだ。そこを発とうと決意した根底には、彼女の生活に生じた喪失が横たわる。
大切なものを失って改めて存在の大きさを知った、などという言葉はぬるすぎて奥歯がすり減るが、自分の世界に大きな穴が開くほどの喪失なら、足場が抜けて、世界の捉え方が変わることはあるだろう。また、大切なものを失った大きな穴をすっぽり覆うようなかたちで、かけがえのないものの輪郭が、新たに露わになることもある。
「欲しいものがやっとわかってきた」と増田は言う。そして、「憎しみに時間を使う余裕がもうない」ということも。
今回展示されるのは、「山」の一点だ。過去最大級の「山」は、145×145cm の大作で、2022年8月に新宿・眼科画廊で行われた展覧会・公開制作ワークショップ「夏の終わりのキルトパーティー」にて参加者とともにつくったキルトと、思い出の布、増田の普段着を縫い合わせてつくられた。同ワークショップには男性の参加者も多く、「傷の連帯ではない状態でも、アートの場に人を招き入れることができるようになった」と増田自身が手応えを感じた機会でもあった。そこにかつての憎しみや禍々しさはなく、代わりに穏やかな生活の匂いがある。
また、今回新たな試みとして取り入れられたのは、刺し子だ。いつか取り組まなければと思っていながら先延ばしにしていたという刺し子を、本作から取り入れるに至った背景にも、やはり喪失の存在がある。彼女の真ん中に空いた大きな穴を埋めるには、工程の多い手作業に没頭する時間が必要だった。油断をすれば泉のごとく湧いてくる悲しみを針先にこめ、糸を布に縫い込んでいく。その時間はまさに、祈りそのものではなかったか。
光に照らされて透けて見える山は神々しく、裾広がりのローブを着た天女が空に向かって祈りを捧げる姿をも彷彿させる。
彼女は繁華街を抜け出し、山の裾野を歩き出した。
彼女はこれからどんな景色を見るのだろう。
〔協力〕
佐々木ののか(statement)
うつゆみこ(photo)
〔主催〕去勢合同会社